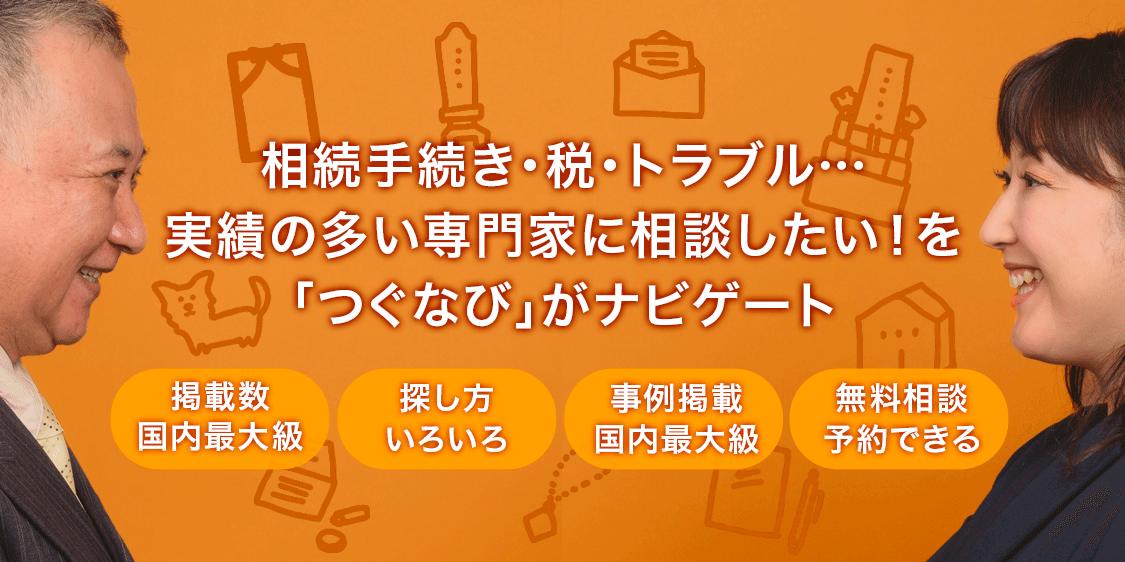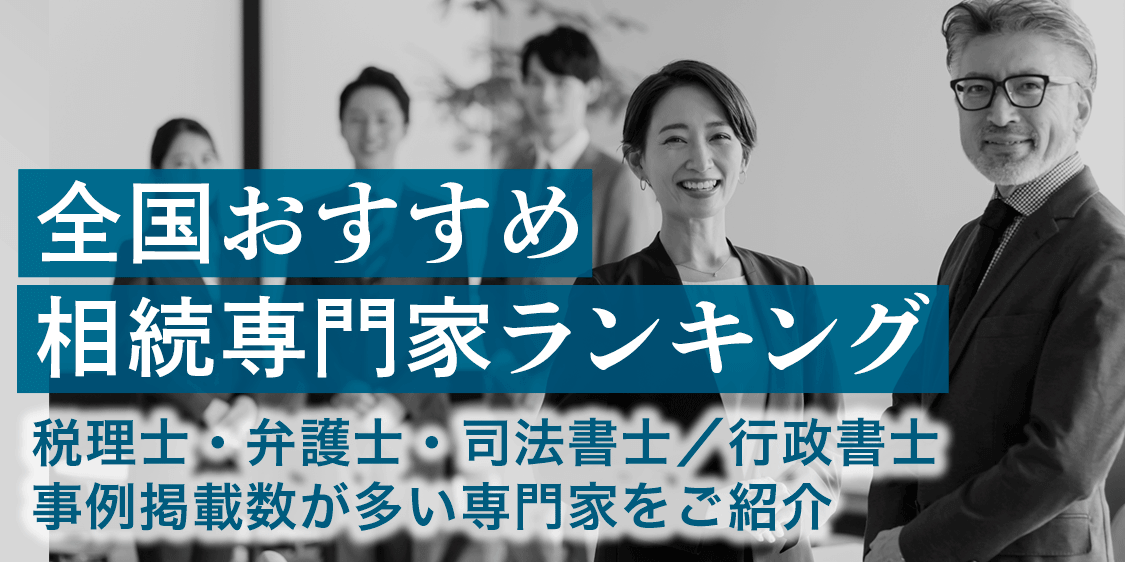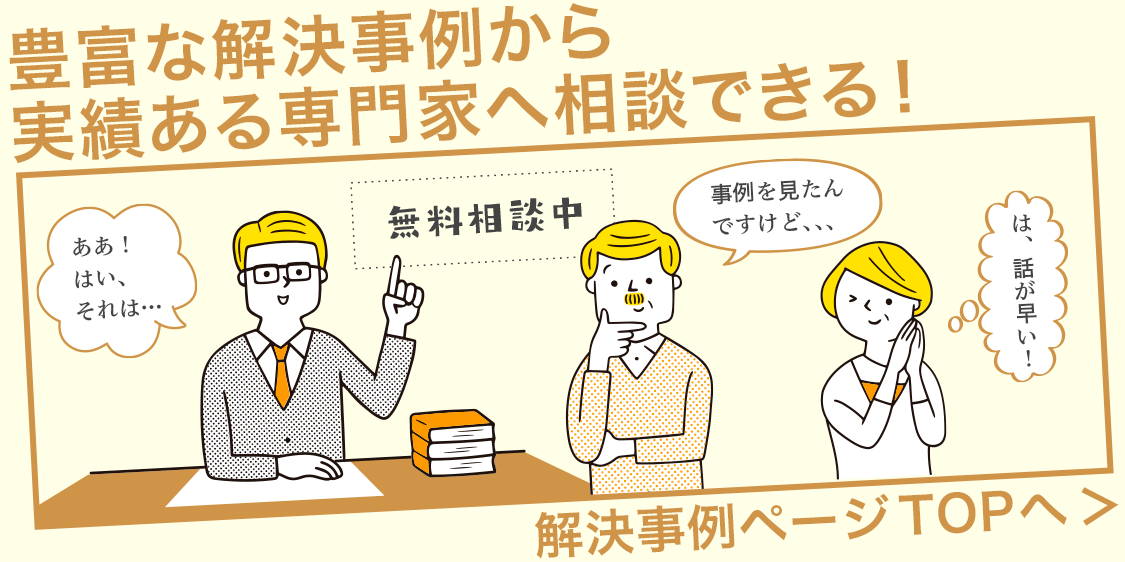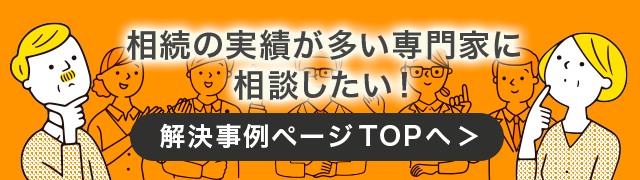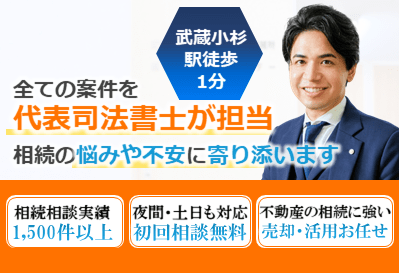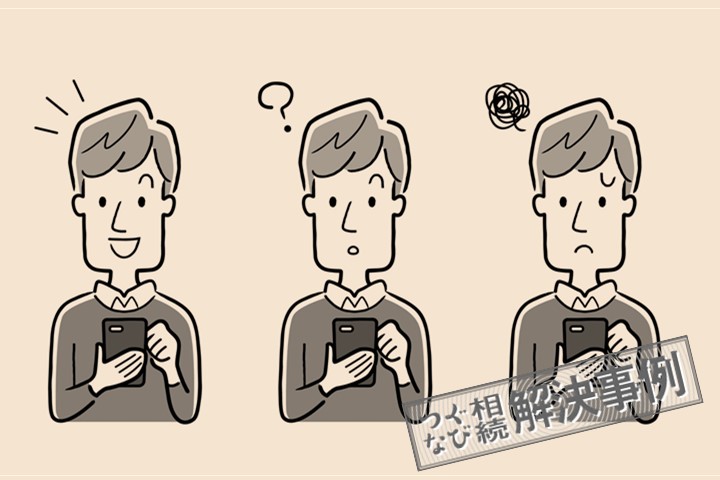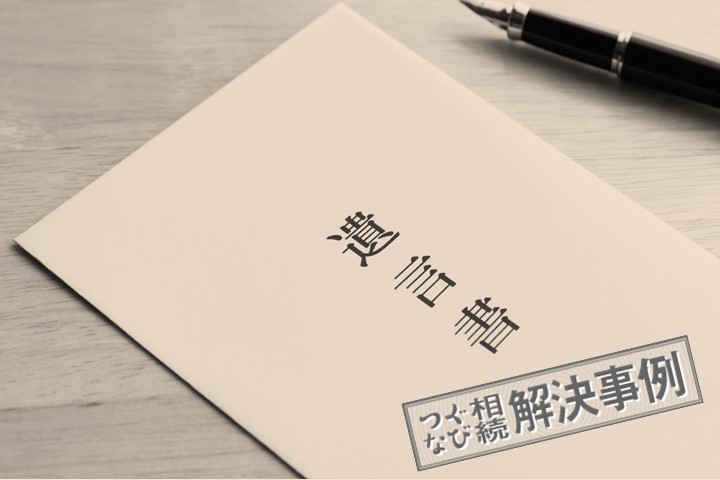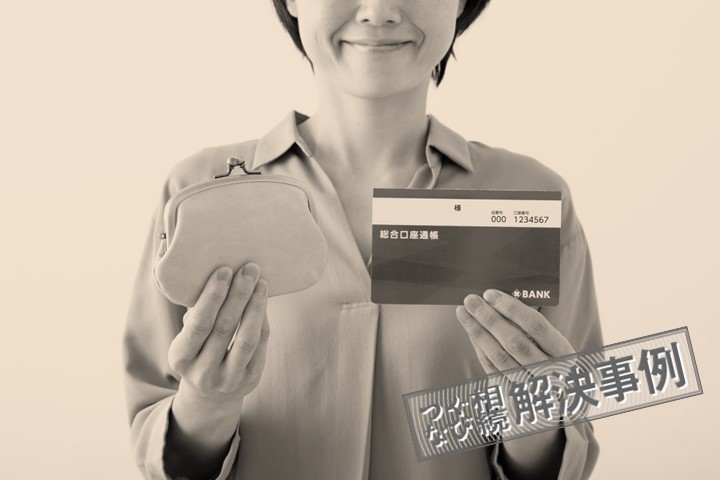実績豊富な専門家ランキング
全国の税理士・弁護士・司法書士/行政書士から、
事例掲載数の多い専門家をご紹介
- 税理士
- 弁護士
- 司法書士・
行政書士
地域を選択してください
北海道・東北
関東
中部
関西
中国・四国
九州・沖縄
最新解決事例
つぐなびを使う4つのメリット

お客様のご希望により合った
相談先が見つかる
士業事務所の掲載数は国内最大級!
事務所紹介情報が充実しています。

いろいろな比較ができるから
相談先探しもカンタン
士業、地域、料金、事例などで
比較が可能!

豊富な解決事例から
実績のある相談先を選べる
解決事例掲載2,000件以上!

ご利用がはじめての方も
気軽に相談できる
つぐなびから無料相談の予約が可能!
最新コラム
-
相続税は誰に、いくらかかるもの? 相続財産調査から申告までの流れ 相続税は誰に、いくらかかるもの? 相続財産調査から申告までの流れ
相続税は亡くなった人の財産にかかる税金です。財産額や相続人の人数によって税金がか…... 相続税は亡くなった人の財産にかかる税金です。財産額や相続人の…...
-
相続税の延納・物納とは 利用できる条件や注意点について解説 相続税の延納・物納とは 利用できる条件や注意点について解説
相続税は、ご家族が亡くなってから10カ月以内に現金で一括納付するのが原則です。し…... 相続税は、ご家族が亡くなってから10カ月以内に現金で一括納付…...
-
相続税の申告期限はいつまで? 延長できるケースや間に合わない場合のペナルティ、対処法も解説 相続税の申告期限はいつまで? 延長できるケースや間に合わない場合のペナルティ、対処法も解説
相続税の申告は、被相続人が亡くなったことを相続人が知った日の翌日から10ヵ月以内…... 相続税の申告は、被相続人が亡くなったことを相続人が知った日の…...
-
相続税を軽減できる特例と税額控除 条件や計算式を具体例で解説 相続税を軽減できる特例と税額控除 条件や計算式を具体例で解説
相続の際、遺産の総額が基礎控除を超えると相続税が課税されます。相続税には、基礎控…... 相続の際、遺産の総額が基礎控除を超えると相続税が課税されます…...
-
土地だけの相続税はいくら?計算方法と特例・控除・節税方法、放棄についても解説 土地だけの相続税はいくら?計算方法と特例・控除・節税方法、放棄についても解説
相続財産の中でも特に価値が高いのが土地や住まいのある建物です。土地を相続した場合…... 相続財産の中でも特に価値が高いのが土地や住まいのある建物です…...
船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。
「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。
・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
・本記事を含むコンテンツ(情報、資料、画像、レイアウト、デザイン等)の著作権は、本サイトの運営者、監修者又は執筆者に帰属します。法令で認められた場合を除き、本サイトの運営者に無断で複製、転用、販売、放送、公衆送信、翻訳、貸与等の二次利用はできません。
・本記事の正確性・妥当性等については注意を払っておりますが、その保証をするものではなく、本記事の情報の利用によって利用者等に何等かの損害が発生したとしても、かかる損害について一切の責任を負うことはできません。
・本サイトの運営者は、本記事の執筆者、監修者のご紹介、斡旋等は行いません。
・情報収集モジュール等に関する通知・公表
当社は、本サービスの提供にあたり、利用者の端末に保存された情報を外部サーバーに送信するクッキー、コード、又はプログラム等(以下総称して「情報収集モジュール等」といいます。)を利用します。
当社が利用する情報収集モジュール等の詳細は、以下の通りです。
【情報収集モジュール等の名称】
TETORI
【送信される情報の内容】
https://adm.tetori.link/manual/view/realtime_user
【情報送信先となる者の名称】
グルービーモバイル株式会社
【当社の情報の利用目的】
サイト分析
【送信先での情報の利用目的】
https://www.groovy-m.com/privacy
…閉じる